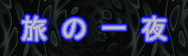
|
第1回 |
|
旅支度をした若者が、町に来た。灰色の上着を着て、皮のような素材のリュックを背負い、右手には護身用の武器にもなりそうな杖を持っている。風に飛ばされそうな帽子を左手で押さえ、今夜の宿を捜していた。もう夕暮れである。野宿するには寒い季節だ。いや、例え暖かい時期であっても、この時代に野宿する人はいない。巡回警備隊に見つかり身元の照合をされてしまう。その危険を犯すことは避けなければならない。例え、今持っているIDカードが完璧なものであったとしてもだ。 若者は町のはずれにある一軒の家の前に来た。小さな平屋であるが、表通りから見える部屋の窓にステンドグラスが嵌めてあった。宗教的な趣のある家だ。ドアをノックすると初老の男が顔を出した。若者は今夜泊めてもらえないかと頼んだ。 「この先、あと5キロも歩けば、宿屋のある街がある。そこまで行く気はないのか?」 「ええ、それは知っていますが、この寒さの中を歩くのは大変ですし、まもなく雪が降るそうですから。」 「ふむ、そういえば、そんなことをニュースで言っていたなあ。だが、わしは一人暮らしだから、なんにもしてやれんぞ。」 「いえ、いいんです。食事は済ませてきましたから、泊めてくださるだけで結構です。」 初老の男は、若者を家に入れた。IDカードを見せなくても中に入れてくれた人はこの男が初めてであった。そのことを言うと、男は、ちらと若者を見て答えた。 「なに、この家には、盗まれる心配をするようなものなど何もありゃせん。わしの命だってなくなって悲しむ者もおらんし、第一、IDカードなど、偽造しようと思えばできんものでもないしな。まあ、こっちで酒につきあわんか。」 若者は言われるままに椅子に腰をおろし、なみなみと酒をつがれたグラスを受け取った。 「一夜の宿のお礼に、私ができることはありませんか。力仕事でも、機械の修理でも、たいがいのことはできます。」 「あんたも面白いことを言うなあ。今の時代にそんな仕事を人間がするわけないだろう。ほれ、そこのインターコムで連絡すれば、30分もせずに、地方公共生活環境改善派遣隊のやつらがやって来て、面倒なことは何でもやってくれる。あいその無い機械どもだが、仕事はちゃんとやる。おまえさんの町では、まだそういうサービスをやってないのかい。」 「いえ、私の故郷の役所にも生活環境改善課があります。が、そういう申し出をするのが旅人のルールだと聞いていますから。」 「まあな、昔はそうだったと何かの本で読んだことがある。ま、わしの酒の相手をしてくれるだけでいい。最近は、町の人もめったに来ないからな。」 若者は、部屋を見回した。西側の壁に、暖炉がある。この家も、壁に埋めこまれた小型空調整備機で完全に室内の空気の状態を管理している、ごくありふれたタイプの個人住宅である。この暖炉は昔の家を模した、ただの飾りなのであろう。その上に、銀の、精巧な細工をした装飾品が一つ置いてある。一目で宗教的な集会でつかわれる類いのものだとわかる。しかし、これは、3体揃っていなければならないはずである。あと二つはどこにあるのか。それを単刀直入に聞いていいものかと考えていると、男は若者に尋ねた。 「こんな田舎町を旅するなんて、一体どこへ行くつもりなんだい。」 「実は、私は少し前まで学生でした。人類学について学んでいたのですが、本で得られる知識だけで人類を全て知ることはできません。だから、世界中の人々と接したい、この目で本当の人間の生活というものを見てみたいと思い旅に出たんです。私は、特に古き時代の名残りを残したまま生活している人に興味があります。ですから、なるべくなら宿屋よりも普通の家庭に泊めてもらっているんです。」 「まあな、人を知るには、一緒に生活するのが一番てっとりばやいからなあ。でもどうしてわしの家にしたんだい?一人暮らしよりも、三世代、四世代が寄り集まって暮らしている家のほうが普通じゃないか。やっぱり、通りから見えるステンドグラスが気になったのかい。そうだろうな、今時珍しいものな。あれは、わしが作ったんだ。なかなかうまいもんだろう。あのデザインにはちゃんと意味があるんだ。愛さ。全てを愛せよ。そういうことさ。だけど、あんな もの本当はもう要らないんだ。ぶち壊しても構わないんだ。ただ、壊したらすぐに警備隊がやってくるに決まっている。そうしたら、そんなことをした理由を話さなきゃならなくなる。あのメカ公に人間の心の問題ってやつを筋道たてて話すなんてこと死んでもしたくないね。融通のきかない鉄くず野郎さ、あいつらは。」 若者は、初老の男の話を黙って聞いていた。男は、酒を飲み干して言った。 「あんたのお勉強の役にはたたんとは思うが、わしの話を聞いてくれるかい?」 若者がうなずくと、男は話し始めた。 |
|
第2回 |
|
あんたも気付いているだろうが、わしは宗教家だった。世の人々に神の教えを説くのがわしの仕事だった。天命だと思っておった。一人でも多くの人を神のもとへ導きたかった。それも、他の宗教家よりも早く数多く、わしの教会の信者にしたいと願った。宗教にそんな野心を持ち込んじゃいけなかったんだ。だが、わしは、あせっていた。ただでさえ、人口は減少しつつある。各宗派が信者を取り合うようになるだろう、その前に確かな地位を築いておきたかったんだ。 それで、わしが考え出したのは、神の教えの理想を具体的な形にして人々に見せることだった。人は目に見えるものを信じる。あの修理屋の機械が無人で派遣されると聞いたとき、住民は反対運動を起こした。だが、実際に自分の目でその安全性が確かめられると、誰もが歯車野郎のことを絶賛した。いくら口で説明したって人は信じない。その目で見るまではな。宗教だって同じじゃないか、不信心者にこれが神の教えの究極の姿だ、と見せつけてやれば納得するはずだ。と、考えたんだ。 宗教の基本は「愛」だ、全てのものを愛する心だ。人々に「愛」を見せるために、わしは愛の女神を創ろうと考えた。限り無く人間に近い、万物を愛する美しき女神、それをこの手でこしらえようと思った。幸い、わしは自動機械工学を学んだことがあった。もちろん、当時も多くの機械野郎は、工場でオートメーションで作られていたさ。注文すれば、好みのロボットも作ってくれる。だが、わしは、既成品じゃ満足できなかった。当時から、ロボットはその仕事に応じたスタイルをしておった。釘を打ったりペンキを塗ったりするのに、人間のかたちをしている必要はない。むしろ、安定が悪くなるし、肝心の脳味噌をしまい込むスペースが少ない。だから、人間型のメカ公は、たいした働きができず、下衆な仕事に使われることが多かった。そんなロボットじゃあ、女神になれるはずがない。第一、メモリーが足りない。「愛」という概念を覚えさせるだけでも、大量のメモリーをくうはずだ。人間としての最低のマナーだって必要だ。完成してからも、多くのことを学習させて、知識を深めさせなければならない。世界にただ一つのロボットになるんだ。自分の手で創りあげようと思った。 力仕事をさせるわけではないから、腕力、脚力なんかは、普通の人間並みに落としても構わない。特殊能力もいらない。不必要な部品を取り去れば、体内に余裕ができる。顔の表情、動作の優雅さを出すための部品がちょっと多目になったが、残りの体内のスペース全てに、学習し、記憶するための機械を詰めこんだ。そう、東洋の神秘と言われる、高性能、小型、安価のチップをたっぷり使った。外見は、過去のあらゆる理想の女性像からデータを作り、わしの好みを加味して決めた。いかにも作り物、といった姿にならぬようにするのが、苦労だった。なにせ、人間的でなければならないんだから。長い月日がかかった。費用が足りなくなって、儀式で使う銀の装飾品も、2つ売ってしまった。女神のおかげで信者が集まれば、すぐに買い戻せると思ったんだ。ようやく完成したときは、涙がとまらなくなったものさ。 女神は素晴らしかった。動き始めたそのときから、彼女は学習を始めた。わしは、偏りのない、全てを愛する心を身につけるよう命令した。彼女は本を読み、歩き回り、その目で多くのものを見て、人の話を聞き、質問をした。どんどん、進歩していった。彼女の愛は深まっていった。噂をきいた人が、遠くからやってきた。からかい半分で来た人も多かった。だが、彼女の愛に触れた人の多くは、愛を信じる者になった。信者は、次第に増えてきた。彼女はますます愛を深めていく。売り飛ばしたものも、買い戻すことができた。女神は、更に学習した。わしは、彼女に、全てを愛する者になってほしかった。全ての山、全ての大地、全ての川、全ての家、全ての慣習、そして、全ての人々を・・・。 だが、ある朝、起きてみると、彼女は壊れていた。物言わぬ部品の寄せ集めになっていた。わしは、急いで、彼女の「自我」を調べた。そこに発見できたのは、ぼろぼろになった彼女の心だった。 彼女は、努力をした。唯一の命令、「全てを愛する」ために。だが、彼女は、全てを愛するためには、あまりにも人間的でありすぎたのだ。人間は、平等な愛は持っていない。どんな人も、必ず、偏っている。全てに愛情を注げる人なんかいやしなかった。どこかで割り切って、余計なものは、捨てていた。だが、彼女はできなかった。与えられた命令が邪魔するのだ。学習すればするほど、「全てを愛せよ」と「人間的であれ」という相反する命令を、実行することが困難になっていく。人間ならば、忘却という便利な機能がある。ロボットは、学んだことは、全て記憶に刻みつけられていくのだ。追い詰められた彼女にできるのは、自滅することだけだった。 女神がいなくなると、信者は皆、わしの元を去って行き、宗教家としての地位を失った。失格者の烙印を押されたんだ。再び、銀の装飾品を売ることになった。今度は自分が食っていくためだ。二度と買い戻すことはできないだろう。どうせ、この時代に、宗教を信じてるやつが何人いるか。 わしの話はこれで終わりだ。つきあってくれてありがとうよ。 |
|
第3回 |
|
初老の男は、若者を寝室に案内した。家具と言える物はベッドと小さな机にパイプイスだけの簡素な小部屋であった。男は若者におやすみと言うとさっさと行ってしまった。若者は、ドアを閉じ、耳をすませた。男は台所へ行き、今度は一人で飲み始めたようだ。飲む合間にぶつぶつとつぶやき、グラスに注いでは歌を唄う。ボトルとグラスがぶつかって音をたて、歌の調子がかなりはずれ、間延びした節回しになってきた。ふと静かになり、一瞬後、いびきが聞こえてきた。あの様子では、もう一度この部屋にくる可能性は、無視していいほどの確率になったと、若者は判断した。 若者は、シャツを脱ぎ、上半身裸になった。ちょうど心臓のあるあたりに右手をあて、少しねじるようにして押した。すると、かすかな金属音をさせて、直径5センチほどの円形に皮膚がはずれ、金属質のような胸板の一部があらわれた。そこには9個のボタンが丸く並んでおり、若者がリズミカルに、ある一定の法則でボタンを押すと、中心部が更にはずれ、穴があいた。リュックから、2種類の薬品を選んで取り出し、その胸の穴から注入した。これで、さっき飲んだアルコールから燃料として利用できる物質が合成される。一般的な食料もエネルギー源とすることができるが、20%の廃棄物が出てしまい、処理に面倒な作業が必要なので、なるべく摂らないようにしている。胸を元に戻すと、今度は目と耳を外し、中から画像と音声それぞれのメモリーのチップを取り出した。今日の日付の付いたケースにしまい込み施錠する。これを開けるためには厳密な手続きと特定の個性が必要とされる。無論、この若者に開けることができるはずがない。新しいチップを嵌め込み、目と耳も元に戻した。 薬品もケースもリュックに戻し、シャツを着た。一日のうちで最も無防備となる5分間の仕事を今日も無事にすませた。この家の主人は、まだいびきをかいて眠ったままである。若者は、ベッドに入ると、自分のリュックを枕の替わりに頭の下に置いた。規則的な寝息をたてるようにし、目を閉じた。警備装置は半径3メートルにセットしている。朝になるまでに、数回寝返りをうち、時々いびきをかき、たまにはよく聞き取れない寝言も言う。いつもと同じ夜である。 明日はこの家を出て、さらに西へと歩いていく。そうして、人と会い、話を聞き、多くのものを見て、記憶していく。ときどき、メモリーチップを回収するための「モノ」がやってくる。チップを受け取り、体に異常がないかをチェックし、新しいチップや、交換部品、燃料などを置いていく。若者は更に旅を続ける。 人類を観察し続けるのが若者の使命だ。ただ観察し、記憶する。自分で考えることはない。自分の行動を悩むことはない。誰が命令しているのかも、目的もわからない。だって、プログラムされていないのだから。 (おわり) |
