�R�����P�@�ٔ������x�͖]�܂����H
�ٔ������x�́A�i�@�̖��剻�̊|�����̂��ƂŁA2009�N�ɓ�������邱�Ƃ����肳��Ă��܂��B�������Ȃ���A���̐��x�̓����ɂ́A����̖��_���w�E���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���ɁA�����`�́A�i�@����̐��x���ɁA�K����������ނ킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��������ɂ����ẮA�Q�����͈�l��[�����l�������܂����A�ٔ������x�ł̖����`�́A�悭�Ă��ٔ����I�o�̒��I�ɓ�����m���̕��������Ӗ��������܂���B�������A�ٔ����́A�����F��݂̂Ȃ炸�A�@�̓K�p���s���̂ł�����A���I�œ������͂̍s�g�҂����肳��邱�ƂɂȂ�܂��i�^�C���c�j�B���̏ꍇ�A�ނ���A�����ɂ͌��͍s�g�҂�I�ԋ@��͂Ȃ����ƂɂȂ�킯�ł�����A������`�ƌĂ�ł��悢���̂�������������ł��B�������A�i�@�̖��剻���X���[�K���Ƃ��Ȃ���A�ٔ������x���}�j�t�F�X�g�Ɍ���Ƃ��Čf�������}�͂���܂���ł����i�����`�̖{���]�|�I�j�B���̂悤�ɁA�����E���������d�������i�@�̕����ɖ����`�𐘂��邱�Ƃ��K���ł��邩�ɂ��ẮA�傢�ɋc�_�̗]�n������̂ł��B
�@���ɁA�i�@�̖����`�́A���@�̖����`�ƑΗ�����\��������܂��B����܂ŁA�����ێ��̕���ɂ����閯���`�̌����́A�g�F�����ׂ����ʃ��[���͊F�Ō��߂�h�A�Ƃ��������̌����Ƃ��ē����Ă��܂����B�������A�ٔ������x�ɂ����āA�@�̉��߂ɍٗʂ̗]�n��傫���F�߂�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ƁA�ٔ����ƂȂ����ꕔ�̐l�X�̈ӌ��ɂ���Ė���I�ɐ��肳�ꂽ�@�����ӓI�ɉ^�p����邩������Ȃ��̂ł��B
�@��O�ɁA�ٔ������x�̂��Ƃł́A�ٔ����ɑI�ꂽ�l�X�̌l�I�ȐM����̌����A�ٔ��̔��������E���邱�ƂɂȂ�܂��B�ٔ��ł́A����̔ƍ߂ɂ͓���̌Y�����Ȃ����邱�Ƃ������ł��B�������Ȃ���A�ٔ����̌l�I�Ȍ������A���҂̐����܂ł����肷��Ƃ������ƂɂȂ�܂��Ɓi���Y�������\�j�A�ٔ��ɑ���M�����͑傫���h�炮��������܂���B����̍߂ł���Ȃ�A�N���ق��Ă����������ƂȂ�Ȃ��Ă͕s�����ƂȂ�܂��傤�B
�@�ȏ�ɏq�ׂ����Ƃ́A���_�̈ꕔ�ɉ߂��܂��A���̑��ɂ��l����ׂ��_�͂���܂��B���s�̌��@�͍ٔ������x�̓�����\�肵�Ă��܂���̂ŁA�{���A���@�������K�v�ƂȂ���ł��B�܂��A�Ñ�A�e�l�ł��A���I�ɂ���Č��͍s�g�҂��I�ꂽ���߁A�����@�\���}�q���āA�A�e�l���ނ̌����Ƃ��Ȃ�܂����B������ɂ��܂��Ă��A�i�@���x�Ƃ́A�������M������悤�Ȑ��x�ƂȂ�Ȃ��Ă͒����I�ɂ͒������͂��܂���B�����ŗ����~�܂��āA������x�ٔ������x�̓������čl���Ă������Ēx���͂Ȃ��̂ł��B�i2007�N�R��25�����M�j
�R�����Q�@�o�[�W�j�A�H�ȑ�w�e���ˎ���
�|����Ƃ�������̏k�}�|
�@2007�N�S��17���A�A�����J�o�[�W�j�A�B�ɏ��݂���o�[�W�j�A�H�ȑ�w�ɂ����āA�j��ň��ƌ�����e�ɂ�閳���ʑ�ʎE�Q�������������܂����B���̎����ɂ��A���������]���ꂽ�Ⴂ�w���̕��X�A�������Đ�[�I�Ȍ����Ɍg����Ă��������̕��X���A�l���̔��œˑR�ɖ���D���A���c�ɂ��e�e�ɓ|��邱�ƂɂȂ�܂����B���̓��́A���⑰���͂��߂Ƃ��āA�A�����J�S�y���[���߂��݂ɕ�܂����ƂȂ����̂ł��B
�@���̔ߎS�Ȏ����́A�P�Ȃ鎖���ł͏I��点�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A�����̉ۑ���c�����ƂɂȂ�܂����B����Ƃ��ďe���p����ꂽ���ƁA�������āA�Ɛl���i�Z�������؍��l�ł��������Ƃ́A����Ƃ������オ��������𔒓��̂��Ƃɂ��炷���ƂɂȂ�������ł��B�����̎����́A�@�Љ�̈��S�A�A�ږ��ƎЉ�I�T��A�B�l�ƍ��Ƃ��邢�͖����Ƃ����ɂ߂ăZ���V�e�B�u�Ȗ��Ɣۂ����ɂ��q�����Ă��܂��̂ł��B
�@���̎Љ�̈��S�Ƃ́A�}�X�R�~�ł̓A�����J�̏e�K�����Ƃ��Ĉ����Ă��܂����A���̖��̖{���́A�A�����J�̏e���̂��̂ɂ���̂ł͂���܂���B�e�̋K���̗L���ɂ�����炸�A�\�͓I�ȃe���͎�i��I���Ɏ��s����邩��ł��B���킪�A�e�ł��낤�Ɛn���ł��낤�ƁA�Љ�A�\�͂̊댯�ɂ��炳��邱�Ƃɂ͕ς�肪����܂��i���{�ł��A����s�s�����e�e�ɓ|��܂����j�A���ɁA�A�����J���{���ɏe�Љ�Ȃ�A���q�̂��߂ɉ��킷��l�����ꂽ�͂��ł��̂ŁA�ނ��뎖�Ԃ͂���قǔߎS�ɂ͂Ȃ�Ȃ������Ƃ����w�E������܂��B�܂�A���̎����ɂ����ẮA�g�N�����������Ԃ��댯�Ȃ̂��h�Ƃ����₢�ɂ����A���̊j�S�����݂��Ă���̂ł��B
�@���̂��Ƃ́A���r���[�ȋ���̋K���̕����A��قNJ댯�ł��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�܂�A�啔���̐l�X���e�������ł��Ȃ��ɂ����āA����ꕔ�̐l�A������\�͓I�ȌX�������l���e�������Ă��܂����ꍇ�̕����A���̌��ʂ́A�͂邩�ɔߎS���ɂ߂Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B����̂ɁA��������邱�Ƃ�C���Ƃ��鍑�Ƃ��g�����I�ȗ͂�Ɛ肷��h�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A���ꂪ�O�ꂵ�Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���h���Ȑl�X�́A�\�͎�i�����l�ɁA��Ɏ���̐����A�g�́A���Y����������邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�@���̂悤�ɍl���܂��ƁA���{�́A�댯�l����W�c�ɖ\�͓I�Ȏ�i��^���Ȃ��悤�ɍő���̓w�͂��X���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�������āA���̖��́A���ێЉ�Ɏ��_���ڂ��܂��ƁA�j�g�U�h�~���i�m�o�s�j�̐��̖��Ƃ��d�Ȃ�܂��B�ꕔ�̖\�͓I�ȍ��Ƃ��A���|�I�Ȕj��͂�������j��ێ������ꍇ�A���h���ȍ��Ƃ́A����̈��S������Ŏ�邱�Ƃ͂��͂�ł��Ȃ��Ȃ�̂ł��B�����O���킸�A�Љ�̈��S�̂��߂ɂ́A������x�A�����I�Ȏ�i�����҂́g���i�h�ɂ��čl����K�v������܂��傤�B
�@���̈ږ��ƎЉ�I�T��̖��́A���̎������A�؍��Ђ̉i�Z�҂ɂ���ċN�����ꂽ���Ƃ����N�������ł��B�A�����J�́A�����������ږ����Ƃł��邱�Ƃ������āA���E���̗l�X�ȍ�����ږ�������Ă��܂����B���̈Ӗ��ɂ����āA�A�����J�́A�ږ��ɊJ���ꂽ���ł͂���܂����A����ł��A�����Ԃ̖��C���a瀂��S���Ȃ��킯�ł͂���܂���B
�@���̖��ɂ́A�����w����Ŏw�E�����悤�ȃA�C�f���e�B�e�B�[�̕�����肪����ł��܂��B����̍��ł��A�ږ��͂���������ǂ������͂������Ȃ��A���邢�́A�ږ��͂�������ǂ��������ł��Ȃ��A�Ƃ������ۂ������Ίώ@����Ă��܂��B�Љ�I�������܂��ƁA�ږ��W�c���A�e����ƍ߂Ƃ��������Љ�I�s���ɑ���Ƃ������Ƃ͋H�ł͂Ȃ��̂ł��B���̏ꍇ�A���ꍑ�Ɉ���I�Ȋ��e�Ǝ�E������݂̂ł͉������܂���̂Łi��Q�ɂ��������̕s�����T�ς��Ă��܂��E�E�E�j�A�ږ����鑤�ɑ��Ă��A�����̎Љ�Ő����邽�߂ɂ́A�ǂ̂悤�ȐS�\���������A�������ׂ��Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ��A������x�₤�Ă݂�K�v������悤�ł��B
�@��O�̖��́A�l�ƍ��Ƃ��邢�͖����Ƃ̊W�́A����ɂ����Ăǂ̂悤�ȈӖ������̂��A�Ƃ����₢�����ł��B�Ɛl�̏o�g���ł���؍��ł́A���̎��������������Ƃ��Ċ؍��l���ʂ���������̂ł͂Ȃ����ƌ��O���L�����Ă���Ƃ���������܂����B�l�ƍ��Ƃ��邢�͖����Ƃ̊W�́A�g�Ȃ��h�Ƃ��͌�����Ȃ��̂������ł��B�Љ�Ƃ́A�X�l�̏W�܂�ł�����܂��̂ŁA�����Ȕƍߎ҂�����܂��ƁA���̐l���ݏo�����Љ�i�����j�ɑ��Ă��s�M�ƌx���̖ڂ��������Ă��܂��̂ł��B�l��`�̎���Ƃ͂����܂����A���炩�̎���������܂��ƁA���݂��Ă��������ӎ���A�C�f���e�B�e�B�[�̖��́A�����ɕ\�Ɍ���Ă��܂��B������̍��ł��A�ƍߎ҂��o���Ȃ��悤�ɁA��ʓI�ȗϗ������Ɋ�Â��ĉƒ��w�Z�ŋ�����s���Ă���̂́A���̂��߂ł�����܂��i���琭��ɂ�����\�̗͂�]��e���̗e�F�͖��E�E�E�j�B�����Ԃ̘A�ѐ��́A���̑��ʂɂ����Ă͋����ӔC�Ƃ��ē����̂ł��B���̂��Ƃ�Y��āg�l�͌l�h�Ɗ�����ċ����Ȕƍ߂ɋy��ł��܂��܂��ƁA���Ƃ����ꂪ�l�̍s�ׂł����Ă��A�����̐l�X�ɑ��Ē��������Q�ƕs���_��^���Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł��B
�@�����̏����́A���̔ߎS�Ȏ������A���P�Ƃ��Ď������ɗ^���Ă��ꂽ���̈ꕔ�ł����Ȃ���������܂���B�������Ȃ���A�������́A�����̋��P��^���Ɏ~�߂邱�Ƃɂ���āA�����S�ȎЉ��z���Ă䂭�Ӗ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�@�����߂Ȏ����ł��钆�ŁA�w������邽�߂ɏ��ƂȂ��ċ]���ƂȂ�ꂽ�����̍s�ׂɁA�l�̖�����낤�Ƃ���l�Ԑ��̑��������o���ꂽ���Ƃ́A�~���ł���܂����B�S���Ȃ�ꂽ���X�̂��������A�S���F��B�i2007�N�S���P�X�����M�j
�R�����R�@�푈�̕����͕s����
���{�����@�̑�X���ɂ́A�g�푈�̕����h�Ɓg��͂̕s�ێ��h�Ɋւ��镶�����u����Ă��܂��B���̏́A����܂ŁA���a���@�̏ے��Ƃ��ĕ]��������A���q���̐ݗ��A���Ĉ��S�ۏ���A�C���N�ւ̎��q���h���ȂǁA���Ƃ��閈�ɁA�������_���ጛ�����߂����ėh��錴���ɂȂ��Ă��܂����B�����A���@�����̂��߂̍������[�@�����肳��钆�ŁA���̌��@��X������������_���A���a�̎����Ƃ����ϓ_����l���Ă݂邱�Ƃ́A�����Ė��ʂȂ��Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B
����ł́A���a�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȕ��@�ŒB���ł���̂ł��傤���H���̖��́A���ɓ����w�R�[�X�ɂ����Ę_���܂������A���E�鍑�̐����ɂ��g�z��̕��a�h���悵�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���ƕ����^�̍������Ƒ̌n�̒��Ŏ������邵������܂���B���̂��߂ɂ́A���݂ɖ@�I�Ɋm�肵�������d���A���͂ɂ��N���s�ׂ��s��Ȃ��K�v������܂��B
���̑��݂̎��ȗ}��������Ă���A�e����`�I�ȍ��Ƃ����݂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���ƊԂ̕��a�͈ێ�����邱�Ƃł��傤�B�������Ȃ���A���̕��a������̂́A���a���ێ����邽�߂̋��ʋK�͂Ƃ��Ă̍��ۖ@��������A����I�Ȍ����ɂ���đ����ɑ��čU�����d�|���鍑������ꂽ���ł��B�Ⴆ�A�����̎��_�ɂ����Ă��A�j�g�U�h�~��������I�ɖ������A�j�J�����s���đ����ɑ���U���͂����Ƃ��Ƃ��Ă��鍑�����݂��Ă��܂��B�܂��A�`�x�b�g�̂悤�ɁA���ɐN�����s���A���̂܂܂̏�ԂƂȂ��Ă��܂�����������܂��B�����������I�ȍU�������ꍇ�A�g���Ȃ��h�ƂȂ�܂��ƁA����́A���@���Ƃ̏������Ӗ����܂��B����ł́A�g�������̏����h�ɂȂ�܂��̂ŁA�l�ԎЉ�̍��{�ϗ��ɔ����Ă��܂��̂ł��B�܂�A�g�S�Ă̐푈���������h�Ƃ����ӂ��ɑ�X�������߂��܂��ƁA���{�����@�́A�N�����Ƃ�e�F���Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�������Ƃ́A�����ʎE�l��f�v�Ȃǂ̃e���ɑ��Ă������܂��B
���������A����E���̘A�����������p���Őݗ����ꂽ���A�́A�N�����Ƃɑ���������̌R���s�����K�肵�Ă��܂��̂ŁA���@���Ƃɑ��鐳�`�̐킢�A�܂萳��̘_������b�Ƃ��Ă��܂��B���{�����@�̑�X���́A���̍��A�̐���̎d�g�݂Ɏ����̖��^��C�����Ƃ��Ƃ�܂����A���ۂɁA���̎d�g�݂��A���{�������҂��Ă����悤�ɋ@�\����킯�ł͂���܂���B���̂Ȃ�A���S�ۏᗝ����ɂ����ď�C�������ɔF�߂��Ă��鋑�ی��́A��C�������ɂ��N���s�ׂɂ͐���̎d�g�݂��������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă��邩��ł��B�����̌R�g������뜜����܂��悤�ɁA��C���������e����`�ɑ���Ȃ��ۏ�͂ǂ��ɂ�����܂���B�܂�A���{���̈��S�́A���A�ɂ���Ă͕ۏႳ��Ă��Ȃ��̂ł��B���ē����̏d�v���́A���̓����������A�����ɓ��{��������Ă��邱�Ƃɂ���̂ł��B
���̂悤�ɍl���Ă݂܂��ƁA�푈�̕������K�����������I�ɗD�z���Ă���A���A���a�ɍv������킯�ł͂Ȃ��悤�ł��B��X���̖��́A���߂̕ύX�݂̂ʼn\�Ƃ̌���������܂����A�������ׂ��푈��N���푈�Ɍ��肵�A���@���Ƃɑ��鎩�q�푈�Ɛ��ِ푈�͔F�߁A���A���吧�x�̂��ƂŌR���̓��������ɔF�߂�����A��قǎ����Ǝ����������A���ے����̈ێ��ɍv���ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�푈���甼���I���߂����������A���{�����́A���ێЉ�ɑ���ӔC�����o���A�ӔC�������Ė@�Ɛ��`�ɂ�鍑�ے�����z���ׂ��A���̐����Ȃ�g�����ʂ����Ă䂭�ׂ����̂ƍl����̂ł��B(2007�N�T���R�����@�L�O�����M)
�R�����S�@�V���̔��̃V�X�e���č\�z�ɂ���
�@�@�V���Ƃɂ��܂��ẮA�Ƌ֖@�ɂ����ē���w����Ă���A���炭�Ĕ̔����x���ێ�����Ă��܂����B�Ĕ̐��x�̔p�~�����x������������A���݂܂ł̂Ƃ���A���{�I�ȉ��v�ɂ͎����Ă͂���܂���B
�@�V���Ƃɂ����܂��Ĕ̐��x�ێ��̍ő�̍����́A�˕ʔz���̈ێ��ɂ���܂��B���ɁA�Ĕ̐��x���p�~����܂��ƁA�˕ʔz����ł��邩�A�������́A�z��������悹���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����咣������̂ł��B�܂��A�����̌����ɂ��p������������Ȃ��V����������邩������܂���B�����Ȃ�܂��ƐV���А�������A�����`���x���錾�_�̑��l�����������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ����O����Ă���̂ł��B�������Ȃ���A���̈���ŁA����̂܂܂ł��ƁA�V���ЊԂɋ����̃��J�j�Y���͓����܂��A�܂��A�Ǝ��̔̔��Ԃ������Ȃ����Ǝx�Ђ́A�V�K�ɐV�����ƂɎQ�����邱�Ƃ��ł��܂���B
�@���̖��̉����̂��߂ɂ́A�܂��́A�g���ɍĔ̐��x��p�~����Ă��˕ʔz�����ێ��ł���h�A�Ƃ������@���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B�����ŁA�V���ȐV���̔��V�X�e�����\�z���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�̂ł����A�V���̔������Ƃ��s���V���ЂƑ����l�b�g���[�N���Ǝ҂Ƃ�������@����Ăƌ��������ł��B���̕����V�X�e���ł��ƁA�V���Ђ��A��ނ�L���̎��M�E�ҏW�Ƃ��������ʂÂ���Ɣ��s���s���A�Ɨ��I�ȗ���ɂ�������l�b�g���[�N�Ǝ҂��A�˕ʔz�����s�����ƂɂȂ�܂��i�������������̊��S�������\�E�E�E�j�B
�@�����l�b�g���[�N���Ǝ҂̐ݗ��ɂ́A�����̐V���Ђ̔̔��ԁi�V���e�Ђ̔̔��X�j���E�ĕ҂�����@�A�V�K�ɐݗ�������Ђ��V���ɍ\�z��������A���邢�́A��z�Ǝ҂̎Q����F�߂镡�������ȂǁA����̕��@���l�����܂��B���̑����l�b�g���[�N���Ǝ҂́A�G�b�Z���V�����E�t�@�V���e�B�̒҂Ƃ݂Ȃ���܂��̂ŁA�e�V���Ђɑ��Ē����I�������ɑ�z�V�X�e�����J�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�܂��A�����T�[�r�X�`���Ƃ��āA�ƒn�ւ̔z�B���������������ƂɂȂ�܂��B
�@���Ȃ��Ƃ��A���̕��@�ł��ƁA�Ǝ��̔̔��Ԃ������Ȃ����Ǝ҂ł��A�V�����Ƃɗe�ՂɎQ���ł���悤�ɂȂ�܂��B���ʂƂ��āA�V���Ђ̐��������A���_�̑��l���́A�ނ���[�܂邩������܂���B�\���̎��R�⌾�_�E�o�ł̎��R�A���тɁA�����̒m�錠���̕ۏ�Ƃ����ϓ_�ɏƂ炵�Ă݂܂��Ă��A�����̑I���̕����L����̂ł�����A�����ă}�C�i�X�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��͂��ł��B�܂��A�����̐V���ЂɂƂ�܂��Ă��A����܂Ōo�c���������Ă��܂����z�����̕��S���啝�Ɍ���܂��̂ŁA�g�D�Ґ��Ǝ��Ƃ̌������̃`�����X�Ƃ��Ȃ�܂��B���ʂƂ��āA�e�V���Ђ��A�w�ǎ҂̃j�[�Y�ɓ��������̍����V���̔��s�𑈂��悤�ɂȂ�܂�����A���{���̐V���V�X�e���́A�啝�ɉ��P����邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i2007�N�T��19�����M�j
�R�����T�@�k���̓y���̓��V�A����̊����v���I
�@���݁A�䂪���ƃ��V�A�Ƃ̊Ԃɂ͕��a���������Ă��炸�A����E���̐�㏈���́A�܂����S�ɂ͏I����Ă��Ȃ��ɂ���܂��B���̂��߁A�����Ԃ̊W�𑁊��ɐ��퉻�����邽�߂ɁA�𑨁A����A�����A�F�O�̎l���̈ꊇ�ԊҘ_�ɉ����āA�����ƐF�O�݂̂̓ԊҘ_�⋤�������_�Ȃǂ��������Ă��܂����B�������Ȃ���A���j�I�Ȍo�܂��猩�܂��ƁA���V�A���k���̓y�̗̗L����{���ɔ��邱�Ƃ́A���炩�ɁA���{���ɑ���̓y�����v�����Ӗ����Ă��܂��B���������܂��ƁA����ɏ��������ł��낤���V�A�Ƃ̕��a���̓��e�ɖk���̓y�̃��V�A������F�߂���܂܂��Ƃ��܂��ƁA����́A����E���̌��ʁA���V�A���̓y�g�����s�����A�Ƃ�����������j�Ɏc�����ƂɂȂ�̂ł��B
�@�͂����āA���̂��Ƃ́A�l�ނ̗��j�ɂ����ĉ����Ӗ����邱�ƂɂȂ�̂ł��傤���H�k���̓y���̔����������A���\�������̈���I�Ȕj���ɂ��\�A�M�̎Q��ƁA�~���̈ӎv�\���ł���|�c�_���錾�̎����\��������ɍs��ꂽ�\�A�R�̐N�U�Ɛ�̂ɂ��邱�Ƃ́A�ǂ��m����Ƃ���ł��B�܂�A�\�A�M�ɂ�鍑�ۖ@�̈ᔽ�s�ׂ��炱�̖��͐������̂ł��B�\�A�M�́A���̍s�ׂ�ĉp�\�Ԃ̖���ł����������^����Ɋ�Â������ȍs�ׂƂ��A�����@�ɂ���Ď����̗̓y�Ƃ��ĕғ����Ă��܂��܂����B
�@�\�A���̎咣�́A��Ƃ��āA��ɐG�ꂽ�����^����ƃT���t�����V�X�R�u�a���̑����ic�j�̐瓇�̕����Ɉˋ����Ă��܂��B�������Ȃ���A����͍��ۖ@�ɏƂ炵�đ�O�����S�����܂��A�T���t�����V�X�R���ɂ̓\�A�M�͎Q�����Ă��܂���B�ł�����A�����̋������́A�k���̓y�̗L�̍��@�I�ȍ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@����A���{���ɂ́A�k���̓y���ŗL�̗̓y�Ƃ���L�͂ȍ���������܂��B�]�ˎ����1798�N�ɂ́A�ߓ��d���ƍŏ㓿�����A�𑨓��ɓn��A�u����{�b�o�C�{�v�̕W���𗧂ĂĂ��܂��B1800�N�ɂ́A���{�����Ɠ��l�ɋ��������~����A���{�̊��������C���܂����̂ŁA���ۖ@��̐��̗v�����[�����Ă������ƂɂȂ�܂��B�����ƂȂ��āA1855�N�ɁA���V�A�Ƃ̊Ԃɓ��I�ʍD���������A�����̋��E���͑𑨓��ƃE���b�v���̊ԂɈ�����邱�ƂɂȂ�܂����B�܂�A�����Ԃ́A���a���ɍ�������肵���̂ł��B���̌�̐瓇�E�����������i1875�N�j�A����сA���I�푈�̃|�[�c�}�X���i1905�N�j�ɂ����Ă��A�k���̓y�͓��{���̂̂܂܂ł���A�̓y�̕ύX�͂���܂���ł����i�ŗL�̗̓y�j�B
�v���܂��ɁA����E���ɂ�����A�������f�������`�́A�g�ȐN�����Ƃɑ���킢�h�ł����B���̎p���́A1941�N�ɕĉp��]�ɂ���Č��\���ꂽ�吼�m���͂���A�A���������錾�i1942�N�j�A�J�C���錾�i1943�N�j�Ɏ���܂ŁA������̓y�s�g�匴������т��Čf���Ă������Ƃ�����A�����������Ƃ��ł��܂��B�������Ȃ���A�����Ɏ����āA���V�A�̖k���̓y�̗L��F�߂�Ƃ��܂��ƁA���ɁA�A���������A�푈�i���͂̍s�g�j�̌��ʂƂ��Ď���̗̓y���g�傳�������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B����ł́A�h�C�c����{�̐N������������߂��A�����̐푈�̑�V�������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��傤�B
����E���Ƃ́A�A�����A�������Ƃ��ɁA���������̖�������ꂽ�킢�ł����B���̔ߎS�Ȑ킢�ƕ���ꂽ�]�����A�킸���Ȃ�Ƃ��l�ނɂ��悫������^������̂Ƃ���Ȃ�A����́A��x�Ɩ@����������A�\�͂ɂ���Ďx�z�����悤�Ȑ��E�ƂȂ�Ȃ����߂̑b��z�����Ƃɂ����đ��͂���܂���B�k���̓y�����A���{���ɂ��̓y�����̏��F�Ƃ����`�ň��ՂɌ��������܂��ƁA�Ăэ��ێЉ�́A�\�͂��x�z����Í�����ɋt�߂肷�邩������Ȃ��̂ł��B���V�A�����͂�k���̓y�̊�����v�����Ȃ��Ȃ鎞�A���̎������A���͂ɂ�鍑�����̕ύX���g�N���h�Ƃ��Ĕے肵������E���̘A�����̑�V���A�͂��߂āA�����Ƃ��Ɏ������A�l�ނɋ��ʂ̉��b�������炷���j�I�u�ԂƂ��Ȃ�̂ł��B�i2007�N�U��13�����M�j
�@�@�@�@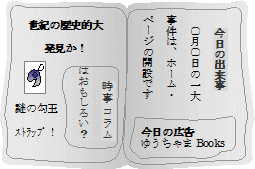 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@