さきほど自分で言ったように、いざという時に動けなければ意味が無い。そこらへんに置いてあったタオル――少しだけ汗臭い気もしたが気にしないことにする――で濡れた髪を拭き、ジャケットの水気を払うようにばたばたと仰いでおく。
ズボンにまで染みてしまった雨に舌打ちをしながらオーフェンは天井を仰いだ。
彼女に言われた一言が、まだオーフェンの胸に突き刺さったままだからだ
『私はオーフェンに守られたくなんて無いわ!!』
自分は彼女の身を案じて行動してきた。さきほどの提案もそうだ。そして、それを彼女もわかってくれていた。それは間違いなかったのだ。
だが、わかっていたのと納得するのでは違う。そして、2人の考えも違っていたようだ。
そして、自分が彼女に考えを押し付けていたことにも気が付いた。
(……馬鹿は俺の方だってことか。あいつがどれだけ止めようと、おとなしく待ってるはずが無いことぐらいわかりきってるのにな)
諦めにも似た感情を抱いたオーフェンだったが、彼女の言葉によって生まれたのはそれだけではなかった。
(支えあう。出来ないことを二人でする……か。何でもひとりでやろうとするのが俺の悪い癖だ……ってのもクリーオウに言われたんだよな)
そこまで考えてオーフェンは思わず苦笑してしまった。結局、全部見透かされてるのだ。
(……二人で闘う……それしかない。いや、それがベストだな)
この考えが最初から除外されていたわけではない。彼女が全くの足手まといになるとはオーフェンも考えていなかったのだ。だが、それでも危険を考えれば彼女に戦いをして欲しくなかった。
(あいつを失うのが怖かったのかもしれねえな…………っと、今はそんなことを考えてる場合じゃなかったな)
ふいに湧き出た考えに困惑したオーフェンだったが、かぶりを振って思い直す。
ここに逃げ込んだ理由。それは天人の遺産への対抗策だ。
クリーオウにも言った通り、肉弾戦では多勢に無勢で話しにならない。魔術を使っても無力化され、その隙に乗じて攻撃されるのは必至。逃げ回っているのも人数的に包囲されればおしまいである。
つまり、手詰まりなのだ。
(くそっ! 守る守らない以前に叩けないんじゃ意味が無い!!)
苛立たしくオーフェンは枯草を手に取った。湿った植物の感触は決して心地よいものではなく、それがさらにオーフェンの苛立ちを誘った。
と、そんなオーフェンの背中に突然重みが加わった。人一人分の重み。
驚いて首だけを回して背後を確認すると、そこには毛布に包まったクリーオウの姿があった。驚いて身を見張るオーフェンにクリーオウはやさしく微笑んだ。
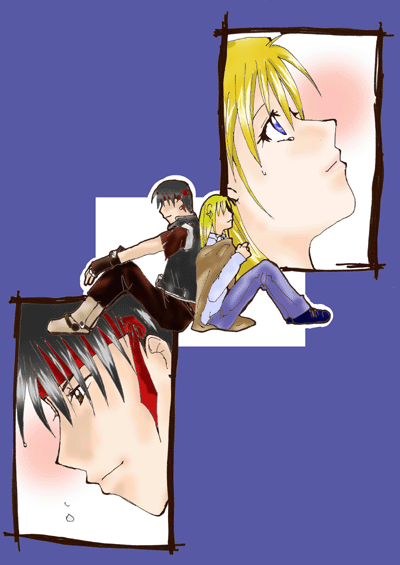
「オーフェン、また一人で考えてたでしょ?」
「……ああ」
「言ったじゃない。できないことは二人で……って」
「…………そうだな」
彼女の重みを背中に感じながら、オーフェンは改めて苦笑した。やっぱりこいつには敵わない、と心でつぶやきながら。
「暗殺者の連中は魔術でなんとかできる。問題は……」
「あの女ね?」
「そうだ。魔術が効かないのはかなりの痛手だ。それに俺の体力も消耗してるし、お前も剣が無い。レキの力で剣を作り出したとしても、100%の力を出せるわけじゃない」
「奇襲は?落とし穴を作って誘導すれば」
「それにひっかかるほど馬鹿じゃないだろう」
「……じゃあオーフェンが全裸になって気を引いてる好きに私が背後から……」
「断じて断る、何が悲しくてこんな大雨の中を全裸で歩かにゃならん。それに逆効果だと思うんだが」
「オーフェンが魔術を放ちぱなしで気を引いて、私が背後から……」
「絶対俺の体力が底を尽きる」
「……根性なし」
「そういう問題じゃねえだろ!!」
「死ぬ気になれば限界くらい超えれるわよ」
「どんなもんだってな! 限界はあるんだよ!! ディープドラゴンにだって不可能はある!!」
「……もうこうなったらオーフェンに脱いでもらうしかないわね」
「だから! 何でそこに戻る!! …………ん、まてよ……」
そこでオーフェンは何かを思いついたように視線を宙に泳がせた。仮説、思考、証明、そして、結論。一通りの答えが出てからオーフェンはクリーオウの方に顔を向けた。
「クリーオウ、お前もたまにはいいこというじゃねえか!」
「え? 裸の作戦を実行するの??」
「そこじゃねえ!!」
大声で反論してからオーフェンは笑った。彼女の言う通り、二人で考えたことによって、一人では到底考えつかないアイディアが浮かんだのだ。
「よし! あとはあいつらがやってくるまで体を休めとくぞ。お前にも一役買ってもらうからな」
「え? ……うん!」
オーフェンの意見が180度変わったことに驚きながらも、クリーオウは満足そうな笑みを浮かべて頷いた。そして、改めてオーフェンの背中に体重を預ける。
「ねえ、オーフェン」
少ししてからクリーオウが話し掛けてきた。背中越しに振り向かず、オーフェンが返事をする。
「さっきはごめんね。守ってもらいたくないなんて言っちゃって」
「いや……俺の勝手だったな。偉そうなことを言ったと思ってるよ」
「本当に? オーフェンらしくないわよ、素直に認めるなんて」
「もとから俺は素直だ」
オーフェンの言葉に吹きだすクリーオウ。背中越しに彼女の震えが伝わってくる。
「何もそこまで笑わんでも良いだろ」
「オーフェンが笑っちゃうような事を言うからよ」
「ったく、なにかってと人をヤクザ扱いしやがって」
憮然と言い放ってオーフェンは前を向いた。まだクリーオウは笑っているようなのでしばらくは振り向いてやらないことに決める。
だが、そんなオーフェンも気分は落ち着いていた。雨に濡れた身体は相変わらず重かったが冷たくは無かった。
毛布越しとは言え背中を合わせている部分から伝わってくる彼女の体温が、オーフェンにぬくもりを与えてくれた。ただ表面上のぬくもりだけでなく、心の中に安らぎをも与えてくれるのだ。
(守る……じゃなかったな。守りたいだ。おれはこいつを守りたいんだ。きっと)
「クリーオウ……いいか、サポートをしてくれるのはありがたいが……」
「無理はするな、でしょ? わかってるわよ」
「そうだな。じゃあ……我は放つ光の白刃!!」
オーフェンが立ち上がり、高々と呪文を叫んだ。
呪文と同時にオーフェンの手から放たれた光熱波はそのまま正面の壁へと衝突する。刹那、膨れ上がった光が膨大な熱量を持ってもろく、崩れかけていた壁を根こそぎ吹き飛ばした。
熱波と土煙、爆風にあたりながらオーフェンは、自分が今破壊した壁の方を見据えていた。クリーオウもいつのまにか立ち上がり、さきほど調達したくわの木の棒を構えている。
そして、2人の見据えた先に人影が現われた。
「さあ、逃走劇はここまでよ? お二人さん」
そこに現われたのは宿を襲撃した連中のリーダーらしき女だった。さきほどはしっかりと見ていなかったため容貌はわからなかったが、年齢はオーフェンと同じくらいだろうか、うっすらとした化粧が塗られた顔には冷笑が浮かんでいた。
「もう一度言うわよ。そのディープドラゴンの子供を私達に渡して頂戴。今なら殺さないで置いてあげるわ」
そういって女はゆっくりと近付いてきた。一歩、歩くごとにポニーテールにされた茶髪――外が雨なのになぜか濡れていなかった――が揺れる。それがまるで振り子のように規則正しいリズムを刻みながら近付いてくる。
「よく言うぜ。暗殺者を差し向けてきたくせに」
「そうよ! それに私たちが、はい、わかりまして、ってレキを渡すと思ってるの!?」
そう言ってクリーオウは棒を構えた。オーフェンも右手を上げ、女を威嚇する。
2人の答えを聞いて疲れたような表情になる女。
「そう、もう少し聞き分けが良いかと持ったんだけど……残念だわ」
大袈裟な仕草でため息をつくと女は一度目を閉じた。大きく息を吸い、腰にぶら下げてある刀を――今まで気が付かなかった――手にとる。
抜刀し、クリーオウの方に向けるとゆっくりと目を開いた。そして……
「まずは……さよなら、お嬢ちゃん」
そう言って女が地面を蹴る。一瞬にして詰めた間合いで女はクリーオウの首をはねるコースで刀を振りぬいた。銀色の残光が目に映り、風が切れるような音が室内に響いた。
だが、そこにはクリーオウの姿は無かった。殺気を感じ取った瞬間、即座に間合いを開き、斬撃を紙一重でかわしたのだ。
そして、剣を振りぬいた姿勢の女に棒を振り下ろす。
それをすばやい反応で避ける女。驚きながらもクリーオウの動きをしっかり把握してあったのだろう。さらに跳ね上がってくる棒をさけ、リーチの届かない場所まで後退する。
「驚いたわ……やるわね、お嬢ちゃん」
本当に驚いたような口調で女。だが、クリーオウは真剣な目で相手をにらんだままだった。そう、彼女も気付いているのだ。動き、間合いの取り方、斬撃のスピード……全てにおいて相手が強いことに
「お嬢ちゃんじゃないわ。私には『クリーオウ=エバーラスティン』って言う名前があるの」
「あら、そう。お嬢ちゃん。そうね……殺される相手の名前を知らないって言うのも不幸ね……」
そう言って女は唇に笑みを浮かべた。全てのものを蔑むような冷たい微笑。そして、目はもちろんの娘と笑ってはいなかった。
「そっちのあなたは?」
「……オーフェンだ。のんきに自己紹介なんてしてる場合じゃねえと思うんだがな」
そう言って今度はオーフェンが地面を蹴った。ジャケットの内側に縫い付けてあった短剣を抜き放ち、水平になぎ払う。
鋭い金属音と同時に火花が瞬いた。そして、同時に離れる二人。だが、今回はそれで終わりではなかった。
「我掲げるは降魔の剣!」
オーフェンの左手――短剣を持っていない手――に剣一本分の質量が生まれる。そして、あたかもその手に短剣が握られているかのように、オーフェンは左手から見えない短剣を投げはなった。
点と点を結ぶように、見えない短剣が女に向かって真っ直ぐに飛んでいく。
が、その短剣は目標に届かなかった。女が盾を短剣の軌道上に掲げたのだ。
そして、まるで盾に吸い込まれたかのように消滅する短剣。
「なるほど……魔術で出来た、空気を圧縮した短剣すらふせげるって訳だ」
「ふふふ……やっぱりあなたは頭いいわね。戦闘中ですら相手のデータを少しでもかき集めようとする姿勢、すばらしい戦闘技能者だわ」
「うるせえ……言っとくが、こっちはてめえの部下のせいで高い宿に泊まれせられるわ、覗き魔にされて大理石をぶつけられるわ、こんなくそ冷たい雨の中を延々走るはめになったんだ。それ相応の報いは覚悟してもらうぜ」
オーフェンはゆっくりと腰を落とす。いつでも飛び出せる体勢を作っているのだ。ふと見るとクリーオウも女に飛び掛るタイミングを計るかのように体勢を変えていた。
「ふ、ふふふ……最高よあなたたち。久々に楽しめそうだわ」
そう言って女は剣を腰の鞘へと落とした。そして同時に指を鳴らす。その瞬間、入り口から数人のッ黒装束の男が現われた。オーフェン達を襲撃したやつらだろう。
「私の名前はカタルシア・ミフォードよ。せいぜい楽しませて頂戴ね、クリーオウとオーフェン」
そして、その言葉が終わらないうちに数人の暗殺者がオーフェン達に向かって飛び出した。全員の手には、間違いなく人を殺すために作られてた刃が握られていた。
だが、オーフェン達は慌てなかった。オーフェンは前方に右手を、クリーオウは頭上にレキを掲げて高らかに叫んだ。
「我は放つ光の白刃!」
「レキ! 吹き飛ばして!!」
同時に起こる爆発。そして、屋根に起こった爆発は家屋全体に致命的なダメージを与え、地面に起こった爆発は暗殺者たちの動きを遅らせた。
崩れる家屋、巻き上がる砂塵。その混乱の中でオーフェンはクリーオウを抱きかかえた。文句も言わず、オーフェンにしっかりと捕まるクリーオウ。それを確認してからオーフェンは呪文を叫んだ。
「我は駆ける天の銀嶺!!」
重力を中和し、ゼロに達した瞬間、オーフェンは地面を蹴った。一瞬にして崩れ落ち始めた家屋の屋根に移り、地面へと飛び降りる。そして、クリーオウを下ろして家屋の方へと向き直った。
いまだに巻き上がる土煙の中、いくつかの人影が見えた。言うまでも無い、あのカタルシアと名乗った女とその部下たちだ。彼女たちの技量からすれば、崩れる建物の下敷きにならずに脱出するくらいは容易だろう。
「オーフェン」
横にいるクリーオウが声をかけてきた。不安そうにではない、決意に満ち溢れている声色でだ。
「ああ……頼りにしてるぜ、相棒」
「任せといて!」
それだけ言ってオーフェンはゆっくりと息を吐いた。全ては整った。身体も、魔術も、思考も、相棒も……
「さて……戦闘、開始だな」
オーフェンのつぶやきは静かに雨の中を舞っていく……
ゆっくりと腰を落して戦闘の姿勢をとるオーフェン達を、暗殺者たちがゆっくりと囲んでいった。