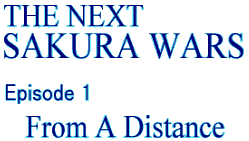
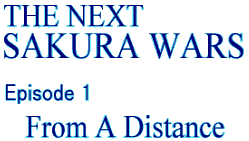
慶応元年、幕府経営の洋式造船所が設置されたのを皮切りに、東京湾口の要衝たるこの地は帝国海軍の一大拠点として急速な発展を遂げていた。
明冶22年に開通した横須賀線の終着駅、ここ横須賀駅にも海軍装に身を包んだ青年たちの姿が珍しくない。
時折しも、下りの急行列車がブレーキをきしませてホームに滑り込んできた。
蒸気に煙るホームを真っ先に駆け抜け改札を飛び出してきた長身の青年──
そう、大神である。東京から優等列車を乗り継いできたのだが、それでもかなりの時間を喰ってしまった。
待合所のあたりを二三度見渡した彼は、それとおぼしき人影に駆け寄っていった。
「あの...失礼ですが、横須賀の司令部からお迎えに頂いた…」
迎えの下士官は不意をつかれたらしく一瞬たじろいだ。
「は、はっ! あなたが大神一郎少尉でいらっしゃいますかっ。米田一基陸軍中将閣下じきじきのご下命に従い、少尉を海軍病院までご案内するようにとの指令を受けて参りました、よろしくお願いいたしますっ!」
「は、ははは...堅い挨拶はいいですから…」
と応えたところで、なんだか当惑したような相手の顔に大神ははっと気づいた。
しまった、俺、モギリの服のままだった!
「な、なにしろ急いでたものだから、これにはちょっとワケがあって...と、とにかく、病院まで急いでもらえますか」
ネクタイをいじりながらバツの悪そうに言い訳する大神。
「も、申し訳ございませんっ!! では、あちらに車を待たせてありますので、どうぞっ!」
── はあ。まったく米田長官から一声かかるとすごいもんだな。
大神は少々面食らいながら、ぴかぴかに磨き上げられた高級蒸気リムジンに急いで乗り込んだ。
車が走り出すやいなや、大神が落ち着かない様子で口を開いた。
「はっ、ご安心ください。お探しのエリナ・フジサキ嬢は生存が確認され、現在海軍病院で施療中であります。医師の診断では生命に別状はないとのことでありまして」
「よ、よかったあ〜...」
クッションの効いた背もたれにへなへなとうずもれる大神。なにしろ帝劇を飛び出してからここまで、何の情報もないまま不安と緊張の連続だったのだ。
「救助に向かった第一水雷戦隊の到着が早かったこともありまして、生存者多数を救助できたのが不幸中の幸いでした」
横須賀へ帰投中だった海軍艦船が救難信号を傍受し直ちに反転、現場へ急行したために迅速な救助活動が行えたのだそうだ。
「それに我が海軍の生存した将兵たちも、自らの命を省みず民間人の救助に全力を尽くしたとのことであります」
「え? 海軍の兵?」
大神が不思議そうな顔をして尋ねる。
「は。当該の民間船には護衛の駆逐艦二隻が随伴しておりましたが...同時に原因不明のまま沈没と...」
「駆逐艦…」
大神の脳裏を悪い予感がよぎった。
「第一水雷戦隊、第二十七駆逐隊、『葦』と『菫』であります」
「菫──」
大神の表情が歪む。
それは、彼があまりにもよく耳にしていた艦名だった。
──病院内は収容者でごった返していた。応援に駆けつけた医師や看護兵が行き交い、ロビーにまで軽傷者があふれ、さながら戦場のような騒ぎとなっている。
受付で確認をとっていた下士官が戻ってきた。
「エリナ・フジサキ嬢は奥の集中治療棟だそうです。こちらへどうぞ」
「は...どうも」
生返事をしながら大神の眼は、何かを探すように人混みの中をさまよっていた。
あいつが...奴がいるはずなんだ。あいつが早々くたばる訳がない。
「少尉、どうか、なさいましたか」
先を行く下士官がいぶかしげな顔をして振り返る。
「い、いえっ、何でもないんです、すみません」
彼は慌てて人並をかき分け奥へと進んだ。何やってるんだ、俺はエリナさんの無事を確認に来たってのに...
エリナの病室は、軽傷者でごった返す一般病棟からはかなり奥まった場所に用意されていた。
「集中治療第二室、...どうぞ、こちらになります」
「あ...ここだね。ありがとう...」
病室に足を踏み入れて──
「...!?」
咄嗟に声が出ずに口をぱくぱくさせる大神。ベッドの脇の長椅子に腰掛けている男──両眼に包帯を巻かれた痛々しい姿ではあったが、旧来の知己を見逃すようなことはなかった。
「か、か、河原崎!」
「...おう、その声は大神だな。来たのか」
男──河原崎和己が長椅子から立ち上がって大神の方へ首を向けた。
「大丈夫なのか、河原崎っ!」
「ああ、見ての通りだ。長く海水に浸かって眼を少しやられたが...じきに良くなる。この通りぴんぴんしてるよ」
彼の話によると、ボートには救助した民間人を載せられるだけ載せ、自分は海中をボートに掴まって耐えていたのだという。
「へええ! さすが、その体力は伊達じゃないな...何はともあれ、まずはお前が無事で安心したよ......大変な目にあったなあ」
「ああ...いまだになにがどうなったのか皆目見当もつかん──」
河原崎は何か言おうとしたが、思い直したように口をつぐんだ。
「それよりもお前、帝国華撃団の方からこの子の様子を見に来たんじゃないのか、話は聞いてる」
「あ、ああ...そうなんだ。無事だったとはさっき聞いたんだけど...どうなんだ?」
「彼女は俺がボートに収容したんでな。今睡眠薬を打ってもらって、あそこのベッドで眠ってる」
「わかった。ええと...」
ベッドのまわりを囲む薄いカーテンをそーっと上げる大神。そこには白い入院着をまとって、静かに寝息を立てている少女の姿があった。
そして側から顔を覗かせた大神の...目と体が、かちんこちんに固まってしまった。
──か、かわいい……
いや、かわいいという表現は誤解を招くかもしれない。彼とてそんなに浮気者な訳ではない...たぶん。
彼女と河原崎の無事を知って安堵した気のゆるみ(?)だったのかもしれない。だが確かに──少女らしい愛らしさを残しつつも、内に秘めた気高さと気品を感じさせる、栗色の髪に彩られたその均整のとれた顔立ち──には、見る者をはっとさせる非凡な美しさがあった。
「──おい、何じーっと黙ってんだ。おまえ、早速一目惚れしてんじゃないだろうな」
河原崎がぼけーっと突っ立っている大神の横っ腹をつっついた。
「いいっ! そ、そんなんじゃないってば」
「どうだか。最近お前なんだか女の匂いが漂ってくるからなあ、そこはかとなく」
実はそれが任務なんだ、とはとても言えたもんじゃない。
「か、からかうのもそれくらいにしといてくれよ...ん?」
笑って懸命にごまかすごまかす大神の目が止まる。あれは──洋風の剣、レイピア?
エリナの側に横たえられているそれは、清潔な白に統一された病室にあって、一種異様ともいえる存在感を放っていた。鞘と握り柄にはアンティークを思わせる精巧な彫り込みが散りばめられている。
彼は左腕を伸ばし、静かにそれを手に取った。ゆっくりと鞘から剣を抜く。
真剣だけが持つ独特の重みが伝わってくる。いや、それだけじゃない、この感じ──
「そのレイピア──彼女のものだ。その子、気を失って波間を漂っていても、その剣だけは堅く握りしめて離さなかったよ。よほど...大切なものらしいな」
音で察したらしく、河原崎がそう説明した。
「そうなのか.....」
大神はそう言葉少なげに応えると、静かにもとあった位置に剣を戻した。
あの剣を手にしたときに襲ってきた── 何とも得体の知れない重圧が、いつまでも大神の両腕を捉えて離さなかった。
「やっほー、大神はーん」
蒸気バイクを従えて、紅蘭がこちらに手を振っていた。
「やあ、迎えに来てくれたんだね。ありがとう、紅蘭」
「なーに、お安いご用や! この子も時々火いれたらな機嫌わるなるしなあ。ほな、いこかぁ」
大神が後席にまたがり、もうもうと白い蒸気を吹き上げてバイクが走り出す。
道行く人の驚きの目が一斉にこちらを向いている。何しろ目立つ、大神も最初は気恥ずかしい感じもしたが、もう慣れた。
「大神はん、ご苦労はんやったなあ。それで...エリナはん、どうやった?」
黄昏時の銀座通りをかっ飛ばしながら、紅蘭がでかい声で大神に訊ねた。
だが、思い当たるフシのある大神の頭には、この質問の常識的な意図が浮かばなかったらしい。
「いいっ! ど、どうだったって、だって今日初めて会ったばかりだし、まだ話もできてないし...」
訳のわからない返事をしてしどろもどろする大神。
「あほか。エリナはんのけがの具合に決まっとるやろ、なに勘違いしとんねんな。...って、大神はん? もしかして、さっそくエリナはんにデレデレなんとちゃうやろなあ...?」
「んぐっ!! へ、変なこといわないでくれよ紅蘭っ! おれはエリナさんの無事を確認に行っただけでっ!」
「はいはい、わかったわかった、冗談やって冗談。なんかムキなっとるとこがあやしいけどなあ」
紅蘭はちょっと意地わるそうにツッコミをいれたが、それ以上は詮索しなかった。こういうあけっぴろげなところが紅蘭のいいところだ。
自分で墓穴を掘って反省しきりな大神。
ああ...まいったな、これがもし由里くんの耳にでもはいったら──
暮れなずむ銀座の美景どころか、さくらのあのジト目姿が頭にはりついて離れない大神であった.....
ご連絡はこちらまで: takayuki あっとまーく sakura.club.ne.jp